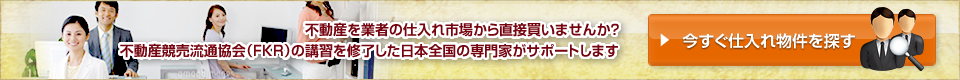公売と競売は、不動産や動産を市場価格より安価に購入できる可能性がある方法として注目されています。
しかし、これらの制度には異なる仕組みや特徴があり、正しく理解していないとトラブルや損失につながることもあります。
本記事では、「公売」と「競売」の違いをわかりやすく解説し、それぞれのメリットやリスクを詳しくご紹介します。
自分に合った選択ができるように、公売物件や競売物件を買う際の参考にしてください。
公売と競売の違いとは?わかりやすく解説
公売と競売の最大の違いは、主催者と目的にあります。
公売は主に税金滞納者の財産を地方自治体や国税庁が売却するもので、税金の回収が目的です。
一方、競売はローン返済を滞納した債務者の不動産を裁判所が売却し、金融機関などの債権者の債務回収を目的としています。
公売物件は主にインターネット公売で取引され、手続きが比較的シンプルで初心者にも利用しやすい点が特徴です。
一方、競売物件は裁判所が主催し、手続きが厳格ですが、物件数が多く、条件に合った物件を見つけやすいというメリットがあります。
このように、目的や仕組みが異なるため、自分のニーズに合った選択をすることが大切です。
| 公売 | 競売 | |
|---|---|---|
| 主催者 | 自治体や国税庁 | 裁判所 |
| 目的 | 税金滞納者から差し押さえた財産を売却し、滞納税を回収するため | ローン滞納者の不動産を売却し、債権者(金融機関など)の債務を回収するため |
| 対象物件 | 不動産、車両、動産(絵画、宝石など)も含む | 主に不動産(住宅や土地) |
| 入札方法 | オンライン(インターネット公売)または直接入札 | 裁判所に直接入札書を提出 |
| 内乱の可否 | 基本的に内覧不可 物件資料(写真や評価書)で状態を確認する | 基本的に内覧不可。 裁判所が作成した評価書や現況報告書で確認 |
| 物件情報の公開 | 自治体や国税庁のウェブサイトに掲載 国税庁 公売情報 | 「BIT(不動産競売物件情報サイト)」や裁判所掲示板に公開 BIT:不動産競売情報サイト 981.jp:競売不動産検索サイト |
| 保証金の必要性 | 必要(物件価格の10~20%程度) | 必要(物件価格の10~20%程度) |
| 手続きの難易度 | 比較的シンプル 初心者でも参加しやすい | 裁判所主催で手続きが厳格 専門知識が必要な場合もある |
公売物件と競売物件の購入方法と注意点の違い
公売物件は地方自治体や国税庁が主催するインターネット公売サイトで物件情報を確認し、簡単に入札登録が可能です。
手続きはオンラインで完結する場合が多く、参加のハードルが低いのが特徴です。
一方、競売物件は裁判所が公開する「BIT(不動産競売物件情報サイト)」で物件情報を確認し、保証金を納付して入札に参加します。
競売は法的な流れが多く、初心者には複雑に感じる場合があります。
どちらの物件も、事前の情報収集と調査が重要です。特に権利関係や物件の状態を把握し、トラブルを避けるために慎重な判断を心がけましょう。
公売物件と競売物件のメリットの違い
公売物件のメリットは、手続きが比較的シンプルであることです。
特にインターネット公売では、オンラインで参加できるため、時間や手間を大幅に省くことができます。
一方、競売物件は裁判所が主催するため、物件情報の透明性が高く、市場に出回らない希少な物件を見つけやすいという点が魅力です。
どちらも市場価格より安価で購入できる可能性があるため、目的や状況に応じて選択肢を検討するのがおすすめです。
ここでは以下の内容について詳しく説明します。
- 共通のメリット:物件が安く買える
- 公売物件のメリット:法的手続きがシンプル
- 競売物件のメリット:物件の選択肢が多い
公売物件と競売物件の共通のメリットは物件が安く買える
公売物件と競売物件の共通する大きなメリットは、市場価格よりも安価で物件を購入できる可能性があることです。
これらの物件は、税金や債務の回収を目的として売却されるため、通常の不動産取引に比べて低価格で設定されることが一般的です。
例えば、同じエリアの物件でも、通常の不動産市場価格の70~80%程度の価格で落札される場合があります。
こうした価格の魅力は、投資用物件を探している人にも非常に人気があります。
公売物件のメリットは法的手続きがシンプル
公売物件のメリットの一つは、手続きが比較的シンプルであることです。
特にインターネット公売を利用する場合、オンライン上で入札が完結するため、初心者でも参加しやすい仕組みが整っています。
また、地方自治体や国税庁が主催しているため、情報の信頼性が高く、公売物件は法律的なトラブルが少ない傾向にあります。
このため、手間をかけずに手続きしたい方には公売物件が適しています。
競売物件のメリットは物件の選択肢が多い
競売物件の大きなメリットは、取り扱い物件数が多いため選択肢が豊富である点です。
裁判所が主催する競売では、住宅地や商業地を含む幅広いエリアの物件が対象となるため、希望条件に合った物件を見つける可能性が高まります。
また、流通量が多いことから、他の入札者との競争が分散しやすい点もメリットです。
特に、立地や広さ、価格のバランスを重視する人にとって、競売物件は魅力的な選択肢となります。
公売物件と競売物件のリスクの違い
公売物件のリスクは、差し押さえ解除による売却キャンセルのリスクがある点です。
税金滞納が解消されると、公売が中止されることがあるため、購入計画が突然変更になる可能性があります。
また、競売物件のリスクは、元所有者や居住者の退去交渉が必要になるケースがあることです。
法的な手続きが必要な場合も多く、購入後に予想外の費用やトラブルが発生することがあります。
いずれもリスクを理解し、事前に十分な情報収集を行うことが重要です。
ここでは以下の内容について詳しく説明します。
- 共通のリスク:内覧できない
- 公売物件のリスク:入札手続きが複雑な場合もある
- 競売物件のリスク:物件の利用目的に制約がある可能性
公売物件と競売物件の共通のリスクは内覧できない
公売物件と競売物件の大きな共通点は、事前に物件の内部を確認できないことです。
通常の不動産取引では内覧が可能ですが、公売・競売では入札前に現地確認ができず、物件の状態や修繕の必要性を正確に把握することが難しい場合があります。
そのため、落札後に大規模な修繕が必要となるなど、予期せぬコストが発生するリスクが高いです。
この課題を解消するためには、事前に公開される資料(評価書や現況報告書)を徹底的に確認することが重要です。
公売物件のリスクは入札手続きが複雑な場合もある
公売物件は自治体や国税庁が主催するため、それぞれの機関ごとに異なる手続きが設定されています。
このため、参加者はその都度手続きの流れを理解し、対応する必要があります。
また、保証金の納付や必要書類の提出など、初心者には手間がかかる場合もあります。
特にインターネット公売を利用する場合でも、登録や入札の流れに不慣れだと、ミスを防ぐための注意が必要です。
このような手続きの煩雑さが、初心者には障壁となることがあります。
競売物件のリスクは物件の利用目的に制約がある可能性
競売物件では、物件が賃貸契約のまま残っていたり、法的に利用目的が制約される場合があります。
例えば、落札した物件に居住者がいる場合、すぐに自分の希望通りに利用することが難しいです。
また、競売物件には管理費や固定資産税の滞納が付随している場合があり、落札者がこれを引き継がなければならないこともあります。
このように、購入後の自由度が低い場合があるため、購入前に物件の権利関係や法的状況をしっかり確認する必要が大切です。
公売物件や競売物件で起こりやすいトラブルと対策の違い
公売物件では、差し押さえ解除による売却中止が典型的なトラブルです。
一方、競売物件では元所有者が物件を意図的に破損したり、退去を拒否するケースが多く見られます。
また、どちらの物件でも、未払いの管理費や修繕費が発生する可能性があるため注意が必要です。
これらのトラブルを防ぐためには、事前に専門家のアドバイスを受けることや、物件情報を徹底的に調査することが有効です。
ここでは以下の主なトラブルについて詳しく解説します。
- 共通のトラブル:占有者が立ち退かない
- 公売物件のトラブル:差し押さえ解除による売却キャンセル
- 競売物件のトラブル:物件が意図的に破損されるリスク
公売物件や競売物件で共通しているトラブルは占有者が立ち退かない
公売・競売物件では、物件に居住している元所有者や賃借人が立ち退きを拒否することが一般的なトラブルとして挙げられます。
落札後も物件の占有が続く場合、法的な手続きを経なければ退去させることができません。
このようなトラブルが発生する理由として、元住民が退去命令を受け入れず、感情的な対立に発展するケースが多いです。
また、賃貸契約が残っている物件では、賃借人に対して契約解除の交渉が必要になる場合もあります。
- 事前に占有者の有無を現況報告書などで確認する
- 交渉が難しい場合は弁護士に相談し、法的手続きを進める準備をする

公売物件のトラブルは差し押さえ解除による売却キャンセル
公売物件の特有のトラブルとして、税金滞納が解消されることで差し押さえが解除され、売却が中止されるケースがあります。
公売は、税金の回収が目的で行われるため、滞納者が支払いを完了した場合、売却を進める必要がなくなります。
このような事態は、公売物件の購入を計画していた入札者にとって、準備や調査が無駄になることを意味します。
さらに、キャンセルによる影響で、次の入札予定まで時間が空いてしまい、別の物件を検討する必要が生じる可能性もあります。
- 公売情報を最新状態に保つため、公式サイトで進行状況を定期的に確認する
- キャンセルに備えて、代替候補の物件を複数検討しておく
競売物件のトラブルは物件が意図的に破損されるリスク
競売物件では、元所有者が退去時に物件を意図的に破損させるリスクが存在します。
このトラブルは、元所有者が差し押さえや競売に対して強い不満を抱いている場合に起こりやすく、窓ガラスや壁の破壊、設備の故意的な破損が見られるケースもあります。
このような行為により、購入後に多額の修繕費が必要となり、落札価格が安くても総費用がかさむことがあります。
また、競売では内覧ができないため、物件が破損されていることを落札後に初めて知るケースも少なくありません。
- 評価書や現況調査報告書を確認し、破損リスクを事前に把握する
- 修繕費を見込んだ上で入札額を調整する
- 受け渡し後は速やかに物件を確認し、必要であれば修繕業者を手配する
売物件や競売物件を探すサイトの違いや注意点は?
公売物件は「国税庁のインターネット公売」や自治体の公式ウェブサイトで探すことができます。
これらのサイトでは、物件情報だけでなく、手続きの詳細も確認可能です。
一方、競売物件は「BIT(不動産競売物件情報サイト)」や地方裁判所の掲示板で情報を収集します。
どちらも公式サイトを活用し、情報の正確性を確認することが重要です。
また、不明点がある場合は、早めに問い合わせを行い、購入計画を慎重に進めましょう。
\会員登録者12万人以上!/
全国の競売物件を簡単検索&比較!
まずは無料会員登録で、最新の競売物件をいち早くチェック
公売物件や競売物件に関するよくある質問
ここでは公売物件や競売物件に関するよくある質問について紹介します。
公売物件や競売物件は誰でも購入できますか?
はい、公売物件・競売物件ともに基本的には誰でも購入可能です。
公売は地方自治体や国税庁が主催し、特に大きな制約はありません。競売物件も裁判所が主催するため、入札資格に特別な制限はありませんが、どちらも事前に保証金の納付が必要です。手続きの理解が必要になるため、公式サイトで詳細を確認しておくと安心です。
公売物件や競売物件に掛かる費用はどのぐらいかかりますか?
購入に必要な費用は以下の通りです。
- 保証金:入札時に必要で、物件価格の10~20%程度(公売)または最低入札価格の20%程度(競売)。落札時には購入代金に充当され、落札できなかった場合は返金されます。
- 購入代金:落札価格がそのまま支払額となります。一括払いが基本です。
- 登記費用:所有権移転にかかる手続き費用。
- 追加費用:未払いの税金や管理費、修繕費などが発生する場合があります。
事前に物件の詳細情報を確認し、必要な費用を計画的に見積もることが大切です。
公売物件や競売物件を購入前はどのような調査を行うべきですか?
購入前には以下の調査を徹底する必要があります。
- 権利関係の確認:抵当権や地役権などの複雑な権利関係が絡む場合があるため、物件明細書や現況報告書を確認し、問題がないか確認します。
- 物件の現況把握:内覧が難しいため、現況報告書や外観、周辺環境を確認し、物件状態をできる限り把握します。
- トラブルリスクの確認:占有者の有無や未払いの費用を調査し、追加の手続きや費用が発生する可能性を把握します。
- 取引事例の確認:過去の落札価格やトラブル事例を参考に、適正な入札額を見積もります。
これらの調査を行うことで、不測の事態を防ぎ、スムーズに取引を進められます。
まとめ
公売と競売は、どちらも市場価格より安く物件を購入できる可能性がある手段ですが、それぞれに特徴やリスクがあります。
公売はシンプルな手続きが魅力で初心者向けですが、差し押さえ解除のリスクがあります。
一方、競売は物件数が多く選択肢が広いものの、法的手続きが複雑です。
事前の情報収集と準備を徹底し、専門家の力を借りながら、自分に合った選択を行いましょう。