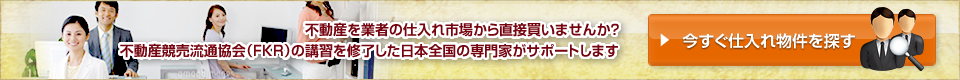「競売物件を購入したけど、前の住人が出て行かない」
「これから購入を考えているけど、住民が出て行かないときのトラブルが心配」
という方も多いのではないでしょうか?
まずは、立退き交渉を行い、円満に進められるようにしましょう。それでも退去しない場合は、法的処置を取り、強制退去してもらう必要があります。
この記事では、競売物件に居座る人への対処法として「引渡命令」と「強制執行」の流れを詳しく解説します。
立退きトラブルに困っている方や、これから不動産競売を始めようとしている方も、トラブルを最小限に抑え、スムーズに物件を引渡してもらうための参考にしてください。
- 競売物件から出て行かないときの対処法
- 立退き交渉に応じる場合の対応
- 立退き交渉に応じない場合の対応
- 競売物件から出て行かないときの引渡命令と強制退去の流れ
- 引渡命令と強制退去時の注意点
\競売物件をお探しの方におすすめ/
競売物件から出て行かないときの対処法
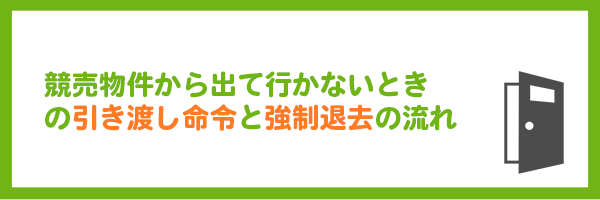
競売物件を購入したものの、「前の住人が出て行かない」というトラブルが起きた場合は、下記に沿って冷静に対処しましょう。
具体的な対処法としては、立退き交渉と法的手続きの2つがあります。
最初は前の住人と交渉し、合意を得て退去してもらい、交渉がうまくいかない場合は、法的な措置で退去してもらう必要があります。
- 立退き交渉に応じる:円満に解決できる可能性を残す方法
- 立退き交渉に応じない:法的手続きを踏む方法
立退き交渉に応じる場合
前の住人が立退き交渉に応じる場合は、費用や退去スケジュールなどを話し合うことが可能です。
まず、住人に対して、競売による物件の所有権移転を正式に伝え、退去をお願いする意向を説明します。
次に、猶予期間を提示した退去日などの交渉を行います。
初めから「所有権者が引越し費用を負担する」必要はなく、以下のような文を送付することで退去の認識を伝えることができます。
引越しの準備が必要であることを考慮し、〇〇月〇〇日までの期間を猶予としてご提供いたします。この間に新しい住居の手配や引越しの準備を進めていただければと思います。
なお、この期間を過ぎても退去が完了しない場合は、やむを得ず法的な手続きを進めることになりますので、その点もご理解のほどお願い申し上げます。
引越し費用を負担する提案を一度してしまうと、住人からさらなる金銭的要求が発生するリスクがあります。
また、法的手続きの際に、その負担を前提に話が進むことがあるため、慎重な対応が求められます。
できる限り費用負担の提案は避け、法的に正当な交渉を進めましょう。
立退き交渉に応じない場合
前の住人が交渉に応じない場合は、「引渡命令の申立て」「強制執行の申立て」「強制退去の実行」といった法的な手続きを進める必要があります。
まず引渡命令を裁判所に申立て、法的に強制退去を実行する手順に進むことになります。
手続きに数か月を要することもあるため、迅速に行動することが重要です。
競売物件から出て行かない理由を解説
競売物件から出て行かない理由として、経済的な問題や知識不足が考えられます。
立退き交渉に応じない人の理由について以下でまとめました。
立退きに応じない理由
- 引越し費用が用意できないことによる居座り
- 競売や退去の必要性についての知識不足
- 強制執行の実施に時間が掛かってしまう
引越し費用が用意できないことによる居座り
前の住人が退去しない主な理由の一つは、引越し費用が用意できないことです。
経済的な理由から新たな住居に移ることができないため、退去を拒むケースがよく見られます。
この場合、交渉を通じて、引越し費用を一部負担するなどの対応を取ることが有効です。
競売や退去の必要性についての知識不足
前の住人が競売や退去の必要性を理解していない場合、問題が長期化することがあります。
特に、競売物件がどのような手続きを経て所有権が移るかを知らない場合、住み続けることができると誤解することもあります。
このような場合は、法的手続きを迅速に進め、正しい情報を伝えることが重要です。
強制執行の実施に時間が掛かってしまう
法的手続きが進んでいる場合でも、強制執行に時間がかかることがあります。
一般的に、引渡命令の申立てから強制執行が完了するまでには、通常3〜6か月程度かかり、手続きの進行具合や住人の対応によっては、この期間がさらに長引くこともあります。
そのため、強制執行までの半年間は住み続けるといったケースもまれにあります。
競売物件から出て行かないときの引渡命令と強制退去の流れ
競売物件で「立退き交渉」に応じない場合、「引渡命令」と「強制執行」による対応が可能です。
まずは引渡命令を申立て、その後、執行官による強制退去の手続きに進みます。
主なステップは以下の通りです。
裁判所に物件の引渡を求める申し立てを行います。
落札代金を全額支払ったのち裁判所への引渡命令申請が可能です。
引渡命令が出た後、執行官に強制退去を依頼します。
執行官が前の住人を強制的に退去させます。
物件の確認や必要な修繕を行い、正式に引渡を完了させます。
以下にて詳しく解説します。
1.裁判所への申立て
競売物件の新所有者が物件を占有している住人に対して退去を求める際、最初に行うのが裁判所への申し立てです。
この手続きにより、法的に住人に物件を明け渡す義務があることを確認し、引渡命令や強制執行の申し立てをすることができます。
裁判所への申し立てとして以下の書類を準備する必要があります。
- 不動産引渡命令申立書
- 申立手数料:相手方の数×500円分の収入印紙
- 予納郵便切手:(110円×申立人の人数)+(1,220円×相手方の数)
- 図面の写しのコピー:引渡しの対象が建物の一部である等、対象を特定するため
- 資格証明書:申立人もしくは相手方が法人の場合のみ必要
- 調査報告書:相手方が所有者以外の占有者の場合で、物件明細書の占有認定と違う場合のみ提出
- 支払の催告をしたことを証明する書類の写し
相手方が複数の場合の注意
相手方が複数の場合は、1通の申立書で申立てをするのではなく、なるべく相手方ごとに申立書を作成するようにしてください。
個別で作成する理由は以下の通りです。
- 個別の責任を明確にするため
- 異なる主張や対応が必要になるため
- 判決や命令の執行が相手ごとに異なる場合があるため
法的なリスクを軽減するためにも相手ごとに申立書を作成することで、手続きを円滑に進めることができるでしょう。
参考:東京地方裁判所|不動産引渡命令の申し立てについて
2. 引渡命令の申立て
裁判所に申し立てが受理され、住人が自主的に退去しない場合、次のステップとして「引渡命令」を申立てます。
これは、裁判所が住人に対して物件の退去を命じる法的な措置であり、住人が従わない場合は強制執行に進むことになります。
引渡命令が出された後、1~2期間程度の期間を経て命令が確定します。
この期間中、住人が異議を申し立てる可能性がありますが、異議が認められない場合は命令が正式に確定し、次の段階に進むことになります。
2. 強制執行の申立て
住人が引渡命令に従わない場合、所有者は「強制執行」を申立てることになります。
その際は以下の書類が必要です。
- 執行文の付与された引渡命令正本
- 引渡命令正本の送達証明書
- 当事者の資格証明書
- 強制執行費用の予納
裁判所から強制執行が認められると、執行官が指名されます。執行官は物件を訪れ、住人に対して最終的な退去命令を伝え、強制的に物件から退去させる準備を進めます。
その際、執行官は住人に強制執行が行われる旨を正式に通知します。この通知を受け取った住人が退去することもありますが、従わない場合は強制的な退去が実行されます。
参考:東京地方裁判所|引渡命令の申立てから強制執行の申立てまでの手続の流れ
3. 執行官による強制退去の実行
強制執行が決定すると、執行官が住人に対して実際に強制退去を実行します。
これは、法的に住人を物件から排除するための最終手段です。
まず始めに、執行官は指定された日に物件を訪問し、住人に対して即時退去を命じます。住人が退去に応じない場合、執行官は強制的に退去を実行します。場合によっては、警察の立ち会いを求めることもあります。
この際、住人が物件に荷物を残した場合、その荷物は執行官の指示により一時的に保管され、一定期間が過ぎると競売処分されます。
執行官が強制退去を完了させた後、物件は正式に新所有者に引き渡されます。物件の状態を確認し、必要に応じて修繕や清掃が行われます。
4. 強制執行後の対応
強制退去が完了した後も、新所有者として物件の管理にしっかり対応する必要があります。
特に物件の損傷や残された荷物の処理など、次の入居者のために迅速な準備を進めることが重要です。
いち早く以物件の状態を確認し、セキュリティや清掃を行うことで、今後のトラブルを防止します。
その際は以下の点を重視しましょう。
物件の状態確認
退去後、物件に損傷がないかを確認し、必要に応じて修繕やクリーニングを行います。強制退去の場合、物件が荒らされている可能性もあるため、速やかに対応することが重要です。
費用の精算
強制執行には、申立て費用や弁護士費用、執行官の手数料などの追加費用が発生します。これらの費用は占有者に請求することができますが、支払いが得られない場合がほとんどなので新所有者が負担することが一般的です。
セキュリティ対策
強制退去後、再び住人が物件に侵入するリスクを避けるため、鍵の交換を行います。これにより、物件の安全を確保し、今後のトラブルを防ぎます。
引渡命令と強制退去時の注意点
強制退去を行う際には、次の注意点を確認しておきましょう。
まず、手続きに数週間から数か月かかることが多く、早めに行動することが必要です。また、賃借人がいる場合、彼らの権利にも注意を払う必要があります。
法的手続きを進める際には、専門家のアドバイスを受けながら進めることが推奨されます。
強制退去まで数週間から数か月かかる
引渡命令や強制執行は、申立てから実行までに時間がかかることがあります。
裁判所の手続きや執行官のスケジュールにより、数週間から数か月かかる場合があります。そのため、計画的な対応が必要です。
この間、物件の使用ができない場合もあるため、計画的に対処する必要があります。
賃借人の権利を確認し適切な対処をする
競売物件に賃借人がいる場合、彼らにも一定の権利が認められています。
そのため、賃借人に対する法的手続きを進める際には、彼らの権利を確認し、適切な対処をすることが重要です。
無理な強制退去はトラブルの原因となるため、法律に基づいた手続きを行いましょう。
参考:国土交通省|主な権利義務について
まとめ
競売物件から出て行かない場合の対処法には、立退き交渉や法的手続きを進める方法があります。
特に、引渡命令や強制退去の流れを理解し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
スムーズな引渡を実現するためには、早期対応がカギとなります。
\競売物件をお探しの方におすすめ/