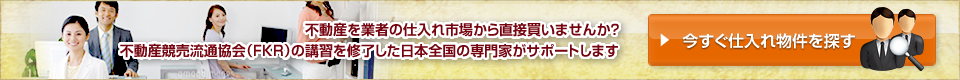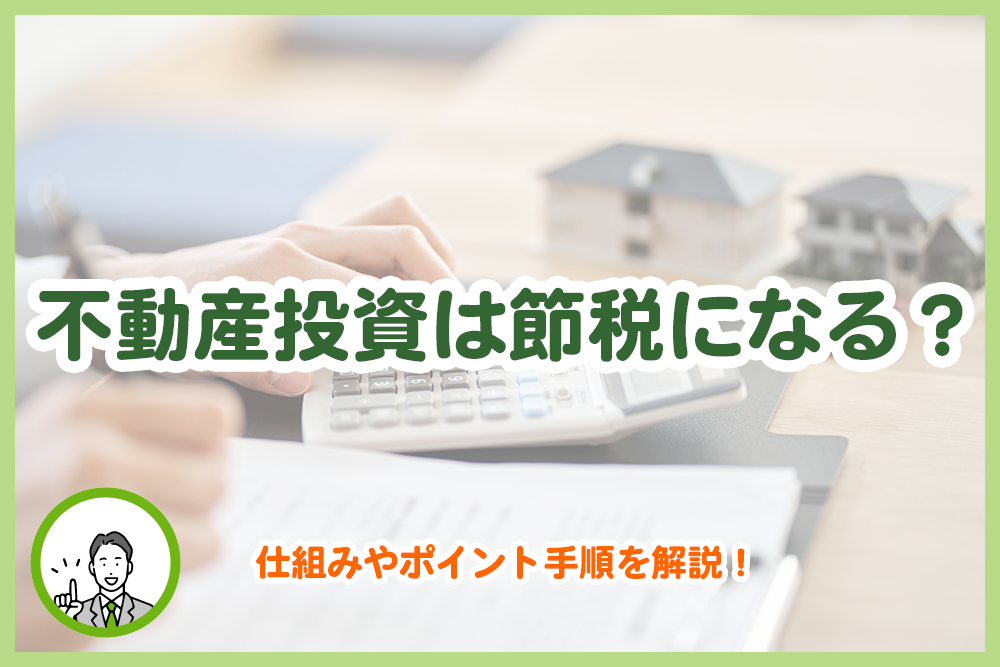不動産投資は収益を得るだけでなく、適切に活用すれば節税にもなります。
特に所得税や住民税の負担軽減を考える人にとって、効果的な手段です。
以下は節税で得られる主なポイントです。
- 減価償却を活用して所得を圧縮できる
- 損益通算で所得税・住民税を軽減できる
- 法人化による税負担軽減ができる
しかし、実際にどのような仕組みで節税ができるのかを理解しなければ、期待した効果が得られません。
本記事では、不動産投資における節税の仕組みや活用方法について詳しく解説します。
- 不動産投資で節税できる仕組みや節税の方法を解説
- 不動産投資が節税に向いている人、向いていない人
- 不動産投資で節税になる物件を選ぶポイント
- 初心者でも安心な不動産投資で節税するための手順
不動産投資で節税できる仕組みや節税の方法を解説
不動産投資は、収益を生むだけでなく、適切な税制の活用によって所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
特に、損益通算や法人化の活用によって、税負担を抑えることが可能です。
ここでは、不動産投資で節税できる仕組みや具体的な方法について詳しく解説します。
不動産投資で節税できるのは損益通算できるから
不動産投資では、「減価償却」を活用して会計上の赤字を作り、「損益通算」により給与所得と相殺することで、所得税・住民税を軽減できます。
損益通算とは、不動産所得の赤字を給与所得などと合算し、全体の課税所得を引き下げる制度です。
特に、減価償却を活用して意図的に会計上の赤字を作ることで、所得税や住民税の負担を軽減できます。
減価償却で現金支出なしの経費計上する
減価償却とは、不動産の建物部分の購入費用を耐用年数に応じて分割し、毎年経費として計上する仕組みです。
最大のメリットは、現金の支出を伴わずに経費を計上できるため、不動産所得が赤字になりやすく、節税につながります。
例えば、8,000万円のマンション(建物価格4,000万円)を購入し、耐用年数10年の場合、毎年400万円の減価償却費を計上可能。
この経費は実際に現金支出がなく、利益を圧縮することで税金を削減できます。
4,000万円 ÷ 10年 = 400万円/年
損益通算で所得を圧縮し税負担を軽減
減価償却などによって発生した会計上の赤字は、損益通算を通じて給与所得と相殺することができます。
これにより、課税所得を引き下げ、所得税や住民税の負担を軽減できます。
例えば、あなたは年収1,000万円のサラリーマンとします。
年間家賃収入が500万円あり、経費(減価償却費を含む)が700万円の場合、200万円の赤字が発生します。
500万円 – 700万円 = -200万円
この200万円の赤字を年収1,000万円と損益通算すれば、課税所得が800万円に圧縮され、適用される所得税率が下がります。
結果として、最終的に支払う税金額は年収800万円の人と同程度になります。
そのため、減価償却費が大きければ大きいほど、会計上の赤字が大きくなるため、より多くの所得を圧縮でき節税効果が高められるのです。
不動産投資にかかる税金の種類は所得税と住民税
不動産投資で得た利益には、主に所得税と住民税が課されます。
不動産所得の額によって税額が決まり、適切な節税対策を行わないと税負担が増える可能性があります。
それぞれの税の仕組みと計算方法について詳しく解説します。
所得税の仕組みと計算方法
所得税は、累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率が高くなる特徴があります。
不動産所得も給与所得と合算され、課税対象となります。
所得税率は以下のように段階的に変動します。
| 課税所得の金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例えば、不動産所得が500万円の場合、330万円超~695万円以下の20%の税率が適用されます。
そのため、課税所得を減らせば、適用税率が下がり、節税につながります。
住民税の仕組みと計算方法
住民税は、一律10%(都道府県税4% + 市町村税6%)の税率が適用されます。
これは所得の多寡に関わらず一定であるため、所得税のような変動はありません。
さらに、一定額の均等割も加算された金額が住民税となります。
以下は住民税の計算です。
課税所得=総所得-各種控除
総所得には、給与所得や不動産所得が含まれます。
控除には基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などが適用されます。
税額控除前の所得割額=課税所得 × 標準税率(10%)
税額控除後の所得割額=税額控除前の所得割額-税額控除の額
住民税=税額控除後の所得割額+均等割
住民税には「均等割」という一定額の税金が含まれます。
所得が増えると住民税の負担も増加するため、不動産投資の節税対策が大切です。
住民税は前年の所得を基準に算出され、翌年に支払う仕組みとなっています。
そのため、不動産投資を始めたばかりの年には課税されませんが、翌年度以降の税負担を見越した資金計画が必要です。
所得税と住民税の合計税率を考慮した節税対策
所得税と住民税を合算し、課税所得900万円を超えた場合、最大43%(所得税33%+住民税10%)の税率が適用されます。
不動産投資を活用し、減価償却や損益通算を利用して課税所得を抑えることで、適用税率を下げ、税負担を軽減することが可能です。
適切な税金対策を行うことで、不動産投資の収益を最大化し、手元に残る利益を増やすことができます。
法人化する節税効果を高められる場合がある
法人化すると、不動産所得に対する税負担を抑えられる可能性があります。
特に、個人の累進課税より法人税率の方が低くなるケースでは、節税効果が期待できます。
- 法人税率の適用:個人の所得税(最大55%)に比べ、法人税(最大23.2%)の方が低くなる場合がある
- 役員報酬で所得分散:給与所得控除を活用でき、個人より税負担を軽減できる
- 経費の幅が広がる:社用車、出張費、福利厚生費などを経費計上できる
- 退職金の活用:法人なら役員退職金を計上でき、将来的な節税が可能
ただし、法人化には設立費用や維持コストがかかるため、投資規模や収益状況に応じて慎重に判断することが重要です。
不動産投資が節税に向いている人・向いていない人
不動産投資は節税効果が期待できる一方で、すべての人に適しているわけではありません。
特に課税所得が高い人は節税メリットを得やすい一方で、資金に余裕がない場合は慎重な判断が必要です。
不動産投資が節税に向いている人は課税所得900万円の人
課税所得が900万円以上の人は、不動産投資を活用することで累進課税の負担を軽減できます。
所得税と住民税の合計税率は33%(所得税23%+住民税10%)となるため、減価償却や損益通算を活用することで課税所得を圧縮し、節税効果を得やすくなります。
そのため、給与所得が多いサラリーマンや高所得の個人事業主に適しています。
不動産投資が節税に向いていない人は自己資金に余裕がない人
自己資金が不足している場合、不動産投資による節税を狙うのはリスクが高くなります。
自己資金に余裕がなく、無理な借入をしてしまうと、節税以上に財務的な負担が増える可能性があります。
そのため、購入時の諸費用や修繕費、空室リスクなどを考慮し、安定したキャッシュフローを確保できるかが重要です。
不動産投資で節税になる物件を選ぶポイント

節税効果を最大化するには、減価償却を活用しやすい物件を選ぶことが重要です
物件の種類や構造によって節税効果が大きく異なるため、適切な選定が求められます。
築古・木造物件を選ぶ
築年数が古い木造物件は、耐用年数が短く、減価償却費を多く計上できるため、短期間で大きな節税効果を得やすいです。
法定耐用年数が22年の木造アパートを購入した場合や、築年数が経過しているほど短期間で減価償却を行えるため、課税所得を大きく圧縮できます。
マンションよりも一棟物件を選ぶ
一棟物件は、区分マンションに比べて建物割合が高いため、減価償却費を多く計上できるメリットがあります。
特に、築古のアパートや戸建て賃貸は、建物部分の割合が高くなるため、節税効果を最大化しやすいです。
一方で、一棟物件は管理や運営の手間がかかるため、運用コストとのバランスを考慮する必要があります。
減価償却期間が残っている物件を選ぶ
減価償却期間が残っている物件を選ぶことで、購入後すぐに減価償却費を計上でき、課税所得を効果的に圧縮できます。
特に、耐用年数を超えた築古物件(法定耐用年数を短縮可能)を選ぶことで、数年間で大きな節税効果を得ることが可能です。
ただし、減価償却期間が短すぎると、売却時に譲渡所得税が発生するため、長期的な資産管理計画が必要になります。
初心者でも安心な不動産投資で節税するための手順
不動産投資で節税を成功させるには、事前の計画が重要です。
初心者でもスムーズに進められるように、具体的な手順を解説します。
節税目標を明確にし自身に合った計画を立てる
不動産投資で節税を成功させるには、まず具体的な節税目標を設定し、自身の状況に合った投資計画を立てることが重要です。
節税の目的や手法は人によって異なり、適切な計画を立てることで最大限の効果を得ることができます。
例えば、課税所得が900万円を超える人は損益通算を活用することで所得税率を下げられますし、法人化すれば法人税の適用により税負担を抑えることも可能です。
また、短期間で大きな節税効果を狙うのか、長期間にわたって税メリットを得るのかによって、選ぶ物件の種類や投資規模も変わってきます。
このように、現在の所得状況やライフプランを踏まえた上で、自分にとって最適な節税方法を見極めることが大切です。
具体的なシミュレーションを行い、税理士や不動産投資の専門家と相談しながら投資戦略を設計することで、税負担を抑えながら資産形成を進めましょう。
節税に効果的な物件タイプを選定する
節税効果を高めるには、減価償却しやすい物件を選ぶことがポイントです。
以下のような物件が特に効果的です。
- 築古の木造物件:耐用年数が短いため、短期間で減価償却できる
- 一棟アパート・戸建て賃貸:建物割合が高く、経費として計上できる額が多い
- 耐用年数が短縮可能な中古物件:法定耐用年数を過ぎた物件は、償却期間を短くできる
こうした物件を選ぶことで、節税効果を最大限に活用できます。
不動産ポータルサイトや業者を活用して物件を探す
不動産投資で節税を成功させるには、適切な物件選びが重要です。
物件探しの方法として、インターネットの不動産ポータルサイトを活用する方法と、不動産業者を通じて紹介してもらう方法があります。
ポータルサイトでは、自分で検索条件を設定し、築年数や構造、価格などを比較できます。
一方、投資用不動産を専門に扱う業者に相談すると、非公開の優良物件を紹介してもらえる可能性があります。
そのため併用しながら、希望する節税効果を得られる物件を選定することが大切です。
また、融資条件や減価償却費を考慮しながら、購入後のキャッシュフローが安定するかも確認しましょう。
購入候補物件の詳細を確認し準備を進める
不動産投資で節税効果を最大限に活かすためには、物件購入前の詳細確認が欠かせません。
特に減価償却費の計上しやすさ、建物の状態、賃貸需要、融資条件を慎重にチェックすることが重要です。
まず、建物割合と減価償却費を確認し、節税効果がどの程度見込めるかを計算します。
築古物件や木造の建物は、耐用年数が短いため、短期間で減価償却費を計上しやすく、節税効果が高まる傾向にあります。
その際、修繕履歴や管理状態を把握し、購入後の追加費用が発生しないかも確認しておきましょう。
さらに、物件の立地や賃貸需要を調査し、空室リスクを抑えながら安定した家賃収入を確保できるかを見極めます。
また、金融機関の融資条件も比較し、無理のない返済計画を立てることが重要なため、事前に精査し投資の安全性と、節税効果を両立させる準備を進めましょう。
物件購入と契約時の注意点を押さえる
物件の購入に進む際は、契約内容を慎重に確認し、トラブルを避けるための注意点を押さえることが重要です。
契約書には、売買価格や支払い条件、引渡日などの基本事項のほか、特約条項が含まれていることがあります。
瑕疵担保責任や修繕義務の有無などを確認し、後々のトラブルを未然に防ぎましょう。
また、融資の正式な承認が得られているかをチェックし、想定外の資金負担が発生しないように注意する必要があります。
そのため契約前には、不動産会社や金融機関、税理士と連携し、契約内容のリスクを十分に把握することが求められます。
長期的な節税効果を見据えてプランを調整する
購入直後に短期間で節税効果だけでなく、長期的な視点でのプラン調整が必要です。
例えば、一定期間運用した後に法人化を検討し、法人税を活用して節税する方法や、経年劣化に伴う修繕費用を計画的に経費として計上して、毎年の税負担を抑える運用方法があります。
そのため、将来的な売却時の譲渡所得税を考慮し、出口戦略を設計することも大切です。
不動産投資は単発の節税策ではなく、長期的に税負担を最適化しながら資産形成を進めるための手段として活用しましょう。
不動産投資の節税におけるよくある質問
不動産投資を活用した節税に関して、多くの人が疑問に思う点を解説します。
特に、サラリーマンが投資を始める際のメリットや、赤字でも節税が可能かどうか、確定申告の手続きについて詳しく説明します。
サラリーマンが不動産投資を行う最大のメリットは、安定した給与所得があるため、融資を受けやすく、損益通算を活用して節税できる点です。
不動産投資では、購入時のローンや物件の維持管理費用を経費として計上し、課税所得を圧縮でき、所得税や住民税の負担を軽減することが可能になります。
節税は可能です。
不動産所得の計算では、家賃収入から減価償却費やローン金利、管理費などを差し引きますが、これらの経費が収入を上回ると、会計上の赤字となります。
しかし赤字は、給与所得と損益通算できるため、課税所得を圧縮できます。
確定申告では、不動産所得の計算を行い、必要な経費を計上し、最終的な課税所得を算出しましょう。
必要書類を準備して確定申告書を作成し、e-Tax(電子申告)または郵送、税務署への持ち込みで申告します。
以下は確定申告に必要な書類の一覧です。
- 不動産所得の収支明細(家賃収入、管理費、修繕費、ローン利息など)
- 減価償却費の計算書
- 固定資産税の支払証明書
- 銀行のローン残高証明書
- 不動産の売買契約書や領収書
まとめ
不動産投資は、適切に運用すれば節税と資産形成を両立できる魅力的な投資手法です。
特に、減価償却や損益通算を活用することで、所得税・住民税の負担を軽減でき、高所得者ほどその恩恵を受けやすくなります。
また、法人化することで、税率の最適化や経費の幅を広げることも可能です。
節税効果を最大限に引き出すためには、築古・木造物件や一棟アパートなど、減価償却しやすい物件を選び、資金計画を慎重に立てることが重要です。
物件購入前には、立地や収益性を十分に確認し、契約内容や税制の変更にも注意を払いましょう。
ただし、不動産投資にはリスクも伴うため、自己資金の管理や長期的なプランの見直しが大切です。
専門家のアドバイスを活用しながら、無理のない投資計画を立てることで、節税と安定した収益を確保し、資産を着実に増やしていくことができるでしょう。