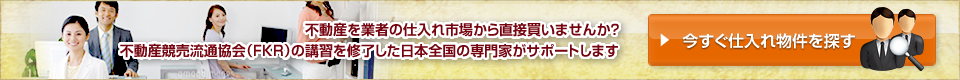「不動産競売に興味があるけれど、具体的な流れがわからない…」と悩んでいませんか?
競売の流れは、「滞納や債務不履行による競売開始」から「物件の明け渡し」まで、多くの段階を経て進みます。
不動産競売は、市場価格よりも安く物件を購入できるチャンスがある一方で、手続きやスケジュールが複雑であるため、初心者にはハードルが高いと感じられることもあります。
本記事では、滞納が発生してから競売が開始され、最終的に明け渡しに至るまで流れをわかりやすく解説します。
競売物件の購入を検討している方や、競売手続きを知りたい方は是非参考にしてください。
\会員登録者12万人以上!/
全国の競売物件を簡単検索&比較!
まずは無料会員登録で、最新の競売物件をいち早くチェックしましょう。
不動産競売の流れについて
不動産競売は、債務者が返済を滞納した場合に、債権者がその不動産を差し押さえて裁判所を通じて売却する手続きです。
通常の不動産取引とは異なる特有のプロセスを経て進行するため、競売に参加する前にその流れを理解することが重要です。
ここでは、不動産競売の流れを具体的なステップごとに詳しく説明します。
- 債権者が裁判所に競売開始の申立てを行う
- 裁判所による差し押さえが宣告される
- 競売物件の現況調査・評価が行われる
- 入札広告で競売物件が一般公開される
- 裁判所の指定する期間内に入札を行う
- 開札が行われ売却許可が決定される
- 代金納付後に登記・物件引渡しが行われる
1.債権者が裁判所に競売開始の申立てを行う
不動産競売の流れは、債権者(通常は金融機関やローン会社)が裁判所に対して競売開始の申立てを行うところから始まります。
申立ての理由は主に、債務者が住宅ローンを滞納し、返済不可能な状態に陥ることです。
ローンを滞納して2~3ヶ月経過した場合に金融機関から「催告書」が送られるようになります。
それでも返納できない場合、最終的に借入金の一括返済が求められる「期限の利益喪失」の通知が送られ、債務者は分割での返済権利を失い、借入金全額の一括返済が求められる状態になります。
金融機関はこの通知後、債務者からの返済が見込めないと判断した場合、不動産を担保として回収する手段を取るために、競売開始の準備を進めます。
2.裁判所による差し押さえが宣告される
競売開始の申し立てが受理されると、裁判所は不動産に対して差し押さえを宣告します。
差し押えとは、債務者がその不動産を自由に処分できないようにする法的な措置です。
この差し押さえが宣告されると、債務者は競売にかけられる不動産を他者に売却したり、抵当に入れたりすることができなくなり、正式に競売手続きへと進むことが可能になります。
この段階で、所有者やその他の関係者には差し押さえが通知され、登記簿に差押えの情報が記載されます。
3.競売物件の現況調査・評価が行われる
差し押さえが完了した後、裁判所は競売物件の詳細な現況調査と評価を行います。
執行官や専門の鑑定士が派遣され、物件の状態、価値、占有状況などが確認されます。
この調査結果は「現況調査報告書」や「評価書」にまとめられ、競売に参加する人が物件情報を確認するための重要な資料となります。
- 物件の状態:建物の築年数、構造、劣化状況などを確認
- 土地の占有状況:元所有者、賃借人、または不法占拠者が住んでいるかどうかを確認
- 法的状態:登記簿に基づく所有権や抵当権などの権利関係の確認
- 周辺環境:近隣の施設や地域情報を確認
この際、物件の市場価値を正確に算定するため、裁判所が指定した不動産鑑定士が評価を行い、物件の評価額、最低入札価格の設定、物件のリスク要因などが評価書にまとめられ一般公開されます。
競売物件の内見は基本的にできないため、入札者はこれらをもとに、入札額を設定することとなります。
4.入札広告で競売物件が一般公開される
裁判所は、物件の調査・評価が完了すると、競売物件の情報を入札広告として公開します。
通常、裁判所のウェブサイトや公告媒体を通じて一般公開され、物件の概要、評価価格、最低入札価格などが記載されます。
この情報公開により、競売物件の入札希望者は物件の詳細を確認し、入札に参加するかを判断することができます。
入札広告は裁判所のウェブサイトや公告媒体で公開され、透明性を確保しつつ広く情報が提供されます。
5.裁判所の指定する期間内に入札を行う
入札広告を確認した希望者は、裁判所が指定する期間内に入札手続きを行います。
以下は基本的な流れです。
- 物件情報を確認し、必要書類を準備する
- 保証金を準備し、入札書を作成する
- 書類を封筒に封入し、裁判所へ提出する
- 開札日を待ち、結果を確認する
入札に参加するためには、必要書類を準備し、保証金を支払う必要があります。
保証金は、通常入札額の20%程度とされており、落札できなかった場合は全額返金されます。
- 入札書:裁判所指定のフォーマットに従い、必要事項を正確に記入したもの
- 暴力団員等に該当しない旨の陳述書:
- 本人確認書類:個人であれば運転免許証やパスポートのコピー、法人であれば法人登記簿謄本など
- 入札保証金振込証明書:保証金を支払った証明書や領収書
- 委任状(代理人の場合):委任内容や代理人の情報を明記
入札のコツとしては、過去に似たような物件があった場合、どの程度の金額で落札されたかを調べましょう。
人気の高い物件は競争率が高く、入札額も高くなりやすいです。
もし、確実に入札したい物件あるのであれば、不動産競売の経験者やコンサルタントに相談して金額を検討しましょう。
6.開札が行われ売却許可が決定される
不動産競売の入札期間が終了すると、裁判所による開札が行われます。
裁判所に提出された入札書を開封、入札者が提示した価格を確認して、最も高い価格を提示した入札者を落札者として決定します。
開札後、裁判所は入札金額の適正性や入札者の資格を慎重に審査し、売却許可を決定します。
この際、不適切な入札や資格に問題がある場合、売却が不許可なる場合があります。
代金が納付された後に登記・引渡しが行われる
競売手続きの最終段階では、落札者が代金を納付し、登記手続きと物件の引渡しが行われます。
売却許可が確定すると、落札者は裁判所が指定する期限内に代金を納付する必要があります。
期限内に納付が行われない場合、落札が無効になる可能性があるため注意が必要です。
代金の納付が完了すると、物件の所有権が正式に買い手に移転し、登記手続きが行われます。
登記が完了した後、物件の引渡しが行われます。
ただし、占有者がいる場合は、裁判所の指示に従い明け渡しを進める必要があります。
任意競売・担保権実行による競売の流れを簡単に紹介
不動産の競売には、大きく分けて「任意競売(任意売却)」と「担保権実行による競売」があります。
それぞれの手続きには特徴があり、流れや注意点が異なります。以下では、それぞれの流れを簡単にご紹介します。
- 任意競売:債務者が金融機関の同意を得て、市場で通常の不動産取引として売却する方法。
- 担保権実行:裁判所が介入して物件を競売にかけ、債権者が債務回収を行う強制的な手続き。
任意競売(任意売却)の流れ
任意競売(任意売却)とは、債務者が債権者(金融機関など)の同意を得て、市場で物件を売却する手続きです。
任意売却は、競売よりも高い価格で物件を売却できる可能性が高く、債務者の負担が軽減されやすいのが特徴です。
以下は具体的な流れです。
債務者が住宅ローンなどの返済が困難になり、滞納が続く状況となります。
債務者が金融機関や債権者に相談し、任意売却の同意を得ます。
任意売却を担当する不動産会社を選び、物件を市場に出します。
通常の不動産取引と同様に、価格を設定して購入希望者を募ります。価格は市場相場に基づき設定されます。
物件が売却され、その売却代金で住宅ローンの一部または全額を返済します。
場合によっては、返済しきれない残債が残ることもありますが、金融機関と相談のうえで対応します。
担保権実行による競売の流れ
担保権実行による競売は、債務者が住宅ローンなどの返済を滞納した場合に、債権者が担保として差し押さえた物件を裁判所の手続きを通じて売却する方法です。
担保権実行による競売は、手続きが法的に定められており、公正で透明性が高い一方、価格が市場より低くなる傾向があるため、債務者にとっては負担が大きい場合もあります。
以下は具体的な流れです。
債務者が住宅ローンなどの返済を滞納し、金融機関が債権回収を開始します。
債権者が裁判所に競売を申し立て、物件の差し押さえが行われます。
裁判所が競売手続きを進め、物件の調査・評価を実施します。評価書が作成され、物件情報が公開されます。
指定された入札期間中に購入希望者が入札を行い、開札によって最高額を提示した人が落札者となります。
落札者が代金を支払い、所有権が移転されます。
裁判所が発行する所有権移転許可書をもとに登記が行われます。
物件に占有者がいる場合は、退去交渉や強制執行手続きを行い、物件を明け渡します。
不動産競売にかかる期間とタイムリミット

不動産競売は、債権者が裁判所に申し立てを行うところから始まり、物件引渡しまで複数の段階を経て進められます。
全体の所要期間は一般的に半年から1年程度とされています。
ただし、物件の状況や裁判所の進行状況によって、短縮または延長される場合もあります。
各段階では期限が設定されており、これを守ることがスムーズな進行において重要です。
たとえば、入札は通常7日間の期間内に行われ、売却許可が確定した後の代金納付期限は1~2週間程度とされています。
このような期限を過ぎると、入札や落札の権利が無効になる可能性があるため、注意が必要です。
| 内容 | 期間 |
|---|---|
| 競売開始の申し立てから差押え | 約1~3か月 |
| 物件の現況調査と評価 | 約2~3か月 |
| 入札と開札 | 約1か月 |
| 代金納付から登記・引渡し | 約1~2か月 |
このスケジュールを把握し、適切な準備を進めることで、競売手続きをスムーズに進めることができます。
裁判所からの通知や期限については、必ず確認し、迅速に対応することが大切です。
タイムリミットを守るためには、スケジュール管理を徹底し、必要に応じて専門家の助言を受けることが成功の鍵となります。
不動産競売の引渡し時のトラブルについて
不動産競売の引渡しでは、所有権を得た落札者が物件を受け取る際に、トラブルが発生する可能があります。
以下は代表的なトラブルです。
- 占有者が退去しないことによる引渡し遅延
- 物件内部の損傷や汚損による修繕の必要
- 債権者の競売取り下げによる競売の中止
それぞれについて詳しく説明します。
占有者が退去しないことによる引渡し遅延
競売物件には、債務者本人や賃借人が占有している場合があります。
所有権が移転しても占有者が物件を退去しないと、引渡しが大幅に遅れる可能性が高いです。
このような場合、裁判所を通じて引渡命令を取得し、その後、実際に立ち退きを強制執行する必要があります。
大まかな流れとしては、以下のとおりです
- 占有者へ自主退去の依頼を出す。
- 応じない場合、裁判所への引渡命令の申請による、退去命令を出す。
- 引渡命令にも応じない場合は、強制執行の実施が行われる。
- 占有者退去後に物件状態の確認と引渡し完了
不動産競売における強制退去(明渡命令)の費用は、物件の規模や状況によって異なりますが、一般的には30万~50万円程度とされています。
また、強制執行の手続きが複雑になる場合や、占有者との交渉が難航する場合には、追加の費用や時間が掛かってしまいます。
このような強制退去にかかる費用は、最終的には新たな所有者が負担することが一般的です。
そのため、占有者との円満な解決を目指し、強制執行を避けることで費用や時間を節約することが大切です。
\競売物件から出て行かない人について/

物件内部の損傷や汚損による修繕の必要
競売物件は「現況引渡し」が原則のため、内部に損傷や汚損があった場合、その対応は落札者の責任となります。
設備の破損やゴミの放置、カビなどの衛生問題、老朽化による劣化が発生している場合も少なくありません。
そのため、事前に評価書や現況調査報告書を確認し、物件の状態を把握することが重要です。
修繕や清掃には数十万円から数百万円の費用がかかる場合もあるため、落札価格だけでなく修繕費用を含めた予算計画が必要です。
また、競売物件を検討する際は、リスクを把握した上で準備を整え、専門家に相談することで、予想外の出費やトラブルを防ぐことが大切です。
不服申立てが通ったり債権者が競売を取り下げたりした場合は入札中止になる
競売手続きが進行している途中で、不服申立てが通ったり、債権者が競売を取り下げたりする場合、入札が中止になることがあります。
これは、裁判所が手続きの適正性を再検討したり、債権者が債務者からの弁済を受け取るなどの事情が生じた際に発生することが一般的です。
不服申立てが認められた場合、手続きそのものが無効とされ、競売の進行が停止します。
一方、債権者が競売を取り下げるケースでは、債務者が全額弁済を完了したり、和解が成立するなど、競売の必要がなくなる場合が該当します。
このような事態が発生した場合、入札参加者が支払った保証金は返還されますが、物件取得の機会を失うことになるため、競売のリスクとして理解しておくことが重要です。
事前に手続きの進行状況を裁判所や競売情報で確認し、リスクを最小限に抑える対応が必要です。
- 債務者の不服申立てが認められた場合
- 債務者が債務を完済した場合
- 債務者の資産に対する差押えが解除された場合
- 手続きの違法性や瑕疵(ミス)が認められた場合
競売物件の流れに関するよくある質問
競売物件の引渡しには、通常、落札後1~2か月程度かかります。
売却許可が裁判所で確定した後、落札者は指定された期間内に代金を納付します。
代金納付が完了すると、裁判所が所有権移転登記や物件の引渡しを進めます。
ただし、占有者が物件に住んでいる場合や、強制退去が必要な場合にはさらに時間がかかることがあります。
状況次第では、数か月以上かかることもあるため、引渡しスケジュールに余裕を持つことが大切です。
競売物件が落札されなかった場合、再度入札が行われる可能性があります。
この際、再入札の最低価格は、通常の評価額よりも引き下げられることがあります。
もし再入札でも落札されない場合、物件は債権者に引渡され、債権者が独自に処分を検討することになります。
一部のケースでは、物件が市場に出回ることもあります。
債権者が競売の取り下げを決定する場合もあるため、状況に応じた対応が求められます。
入札保証金は、競売に参加する際に裁判所に預けるお金のことです。
これは、入札者が落札後に代金を支払わないリスクを防ぐために設定されています。
通常、物件の最低入札価格の20%程度が保証金として必要です。
保証金は、落札者が正式に物件を取得した後、購入代金の一部として充当されます。
一方で、落札されなかった場合や入札が無効となった場合には、保証金は全額返金されます。
参加を検討する際には、保証金を確保しておくことが重要です。
まとめ
競売物件を購入する際の流れは一般の不動産取引とは異なり、独自の手続きやルールが存在します。
引渡しにかかる時間や、落札されなかった場合の再入札、入札保証金の役割などを理解することで、競売への不安を軽減できます。
特に、手続きに関わるタイムラインや費用については事前にしっかりと把握しておくことが重要です。
競売に参加する際には、専門家に相談することでリスクを最小限に抑え、スムーズに進めることが可能です。
\会員登録者12万人以上!/
全国の競売物件を簡単検索&比較!
まずは無料会員登録で、最新の競売物件をいち早くチェックしましょう。