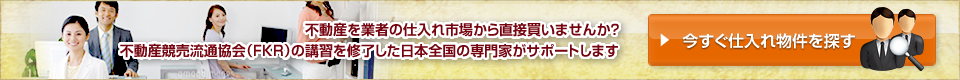「競売物件はやばいって言われているのはなぜ?」
「競売物件を安心して入手できる方法ってあるの?」
競売物件とは、所有者がローンの返済ができずに差し押さえられ、競売にかけられた物件のことです。
そのため、不動産会社で購入する物件と比べると、以下の違いがあります。
- 相場よりも安く購入できる
- 手続きが少なくすぐに購入手続きができる
- 売主非協力的なので内見ができない
- 不動産としての価値が低いケースが多い
珍しい物件や、従来の不動産とほぼかわらないのに半額程度で物件が手に入るチャンスもあるので、一概にやばいといっても、リスクだけではありません。
この記事では、競売物件がやばいといわれる理由や不動産競売のメリットや、リスク回避の方法についてご説明します。
- 競売物件がやばいといわれる理由
- やばい競売物件を避けるためのポイント
- 競売物件を購入するメリット
\最新の競売物件情報をいち早くゲット!/
全国の競売物件を簡単検索&比較!
まずは無料会員登録で、最新の競売物件をいち早くチェックしましょう。
競売物件がやばいと言われる3つの理由

競売物件が「やばい」と言われる3つの理由について解説します。
- 競売物件は内覧できないため内部の状態が不明
- 取引がしにくく資産価値がわかりづらいケースがほとんど
- 不法占拠されている場合裁判所に申し立てが必要
- リフォームや修繕のコストが予想外にかさむ可能性
一般的な不動産購入とは異なり、競売物件には予期しない問題やリスクが存在し、適切な対処をしないと後々大きなトラブルに発展することがあります。
ここでは、その主なリスクを紹介します。
競売物件は内覧できないため内部の状態が不明
競売物件は内覧ができないため、建物内部の様子を確認できません。
厳密にいえば民事執行法第64条の2に基づき、競売物件でも内覧は可能ですが、内覧の許可を得るためには以下の手順が必要です。
- 物件を差し押さえている債権者に裁判所へ内覧の申し込みを依頼
- 裁判所の許可をもらう
- 差し押さえられている債務者に内覧の承諾をもらう
しかし、落札された場合家を失うことになる債務者が内覧許可を出す可能性はほぼないため、実質内覧は不可能に近いです。
内覧ができない場合、老朽化が進んでいる物件や隠れた瑕疵がある場合でも確認できないため、購入後に多額の修繕費用が発生する可能性があります。
競売物件の状況確認は、裁判所が作成した以下の書類で確認することになります。
- 現況調査報告書:不動産の現在の状況、不動産の写真、不動産を占有している者の氏名やその者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載されたもの
- 評価書:周辺の環境や評価額、不動産の図面などが添付されたもの
- 物件明細書:引き継がなければならない賃借権などの権利の有無、土地又は建物だけを買い受けた時に建物のために底地を使用する権利が成立するかどうかなどが記載されたもの
この3つの書類は「3点セット」と呼ばれており、裁判所が運営している競売物件情報サイト「BITシステム」でも閲覧可能です。
取引がしにくく資産価値がわかりづらいケースがほとんど
競売物件がやばいと言われる理由は、取引がしにくく資産価値がわかりづらいケースがあるためです。
例えば、立地条件が極めて悪かったり、工業地域のように特定の用途にしか使用できなかったりと、需要が低い物件は取引がしにくいです。
- 立地条件が悪い物件:利便性が低く、人口も少ない地域の物件
- 再建築不可物件:解体後、家を建築することができない物件
- 指定区域:土壌の汚染が確認された区域
また、老朽化が進んでいるような物件は資産価値が低いほか、修繕が必要になるので売却しても買い手が見つからないという可能性もあります。
この場合は裁判所が作成した評価書で価値がわかるので、事前に確認できます。
評価書以外にも、市場価値を正確に把握し、リスクを理解した上で購入を検討することが重要です。
不法占拠されている場合裁判所に申し立てが必要
競売物件の中には、空家ではなく不法占拠されている物件もあるため判所に申し立てが必要になる場合もあります。
申立から強制執行までの過程は以下の通りです。
| 申請 | 内容 |
|---|---|
| 不動産引渡命令の申し立て | 不法占拠者がいる場合、裁判所に占拠者の退去を勧告してもらうための申し立てを行う |
| 引渡命令 | 裁判所が不法占拠者に立ち退きと物件引き渡しの通告を行う |
| 催告 | 引渡命令に応じない場合、裁判所、強制執行業者、不動産管理会社の立会いによる交渉と強制執行の予告が行われる |
| 断行(強制執行) | 催告に応じす指定の期日を過ぎても退去しなかった場合、強制的に退去させる |
基本的に、引渡命令から催告までがおよそ1ヶ月、催告から断行まで1ヶ月間の猶予が発生するため、立ち退きまでの期間は最長で2ヶ月弱です。
申立ての費用は申立を行った人が支払うことになります。
執行のための費用は、申立ての手数料がおよそ10万円、強制執行後の不法占拠者の残置物の処分費用が50万~100万円ほどです。
他にも、不法占拠者が反社会的勢力の人間だった場合トラブルに巻き込まれるリスクがあります。
そのため、不法占拠者のいる物件ではないか確認するため、報告書をチェックしておきましょう。
リフォームや修繕のコストが予想外にかさむ可能性
競売物件では、購入前に物件の内部状態を確認できない場合が多く、購入後に想定外の修繕やリフォームが必要になることがあります。
これは、物件の内部状態が購入前に確認できないことが主な原因です。
例えば、屋根や壁の老朽化、配管や電気設備の不具合などが見つかると、修繕費が予想を超えることがあります。
また、築年数が古い物件やメンテナンスが十分に行われていない物件では、修理費用が購入価格を超えるリスクもあります。
| 修繕・リフォームが必要なケース | 理由 |
|---|---|
| 内部の老朽化(壁や床の劣化) | 内覧できないため、事前にわからないことが多い |
| 水回り設備の故障(キッチン、浴室など) | 古い設備や長期間放置された物件に多い |
| 電気や配管設備の修繕 | 安全基準を満たしていない場合、全面改修が必要になる |
| 屋根や外壁の修繕 | 特に築年数が古い物件で発生しやすい |
| シロアリ被害や湿気による腐食 | 木造住宅に多く、修繕が必要な場合は高額になることも |
競売物件を購入する際には、これらのリフォームや修繕のコストも十分に考慮し、予算計画を立てることが必要です。
やばい競売物件を避けるための事前調査ポイント
競売物件でリスクの高いやばい物件は、事前調査を行うことで回避できます。
具体的には、次の2つの方法を使えば、競売物件で問題のある物件を購入してしまうリスクを大幅に減らせます。
- 競売資料をもとに現地調査をする
- 信頼できる銀行員に相談し、物件が担保として適格か判断してもらう
ここでは、この2つについて詳しく説明します。
競売物件が宅地なら競売資料をもとに調査が可能
競売物件が宅地の場合、競売資料をもとに詳細な調査を行うことが可能です。
裁判所が提供している報告書に近辺の写真と詳細な情報が書かれているので、そこから大まかな物件情報を考察することができます。
宅地であれば建物を建てることができる土地なので、解体して新しく建物を建てたり、住宅以外の用途にも活用しやすいでしょう。
また直接現地まで赴き、周辺の状態を調査するのも重要です。
建物の内覧はできませんが、外観を見たり、周辺環境を調べることは可能で、重要な情報を得られます。
- 隣が墓地や線路際など、地価を下げる要因ではないか
- 激しい傾斜や狭い小路など、移動が困難になるような立地ではないか
- 建築基準法に違反しているような立地や建物ではないか
信頼できる銀行員に相談して担保として適しているか確認してもらう
物件の価値を判断するために、信頼できる銀行員に相談して、その物件が担保として適しているか確認してもらいましょう。
担保不適格の物件というのは以下の点で問題があるという証明になります。
- 安全性:融資期間を通じて物件が損壊して消滅しないこと
- 確実性:権利に変動がなく、融資期間中一定の価格を維持できること
- 取引のしやすさ:いつでも売却・現金化が可能であること
これらを満たしていない物件は担保として不適切であるため、物件としての価値が低いことを意味します。
担保として適格であると銀行員からお墨付きを貰えれば、その物件は一定の品質を維持している物件という証明になり、やばい物件ではないということになります。
競売物件はやばいだけではなくメリットも大きい
競売物件はやばいだけではなく、リスクを上回る大きなメリットがあります。
競売物件を購入するメリットは、大きく分けると以下の3つです。
- 築浅、都心の物件が相場の半額で購入できる可能性がある
- 購入手続きが少なく、素早く入手できる
- 不動産会社で取り扱っていないような珍しい物件が見つかる事がある
ここでは、この3つについて詳しく説明します。
築浅で都心の物件が相場の半額で購入できる可能性がある
競売物件のメリットは、築浅で都心の物件が相場の半額で購入できる可能性があることです。
築浅で都心の物件は取引しやすく、傷があってもリフォームすれば見た目が良くなるので不動産価値も上がりやすくなります。
ただし都心の物件は人気が高いほか、競売物件の入札期間は8日間しかないので、普段からこまめな確認が必要になります。
また、一見条件が良さそうな物件でも現地調査報告書には目を通し、問題ないかをチェックしましょう。
より確実に良い物件を入手したいのであれば、競売物件の専門業者に相談するのがおすすめです。
\最新の競売物件情報をいち早くゲット!/
全国の競売物件を簡単検索&比較!
まずは無料会員登録で、最新の競売物件をいち早くチェックしましょう。
購入手続きが従来の不動産購入よりもシンプルで時間がかからない
競売物件の購入手続きは、一般的な不動産取引に比べてシンプルです。
通常の売買では複雑な交渉や契約手続きが発生しますが、競売物件の場合、裁判所を通じて進行するため、迅速に手続きが進みます。」
従来の物件購入の流れは以下の通りです。
- 購入の申し込み
- 住宅ローンの事前審査を受ける
- 契約内容の確認をして締結する
- 住宅ローン契約を結ぶ
- 物件の引き渡し
一方で、競売物件の場合は手続きがシンプルです。
- 保証金を支払い競売物件を入札する
- 落札後代金を納付する
- 物件の引き渡し
また、入札から落札までの期間は長くても8日なので、従来の不動産を購入するよりも早く入手できるので、入居も不動産投資もスピーディに行えます。
珍しい物件を入手できる可能性がある
競売物件では、通常の市場では出回らないような珍しい物件を入手できる可能性があります。
珍しい物件例として、以下のようなものがあります。
- 工事途中で競売にかけられた新築物件
- 山地・準工業地域などの用途が限られている土地
- 土地、建物が特殊な形状をしている物件
こうした従来の不動産業者では扱っているところがないような物件でも、競売物件なら見つかる可能性があります。
そうした土地ならではの利用方法や活用方法がある場合、格安で購入できる競売物件は収益性の高い物件となる可能性もあり、不動産投資として購入する価値は十分にあるでしょう。
競売とは?競売物件とは?流れや必要書類についても解説

競売とは、主に借金の返済が滞った際に、債権者が裁判所を通じて債務者の資産を売却し、その代金で債務を回収する法的な手続きのことです。
この競売の対象となる資産の中でも、特に不動産が「競売物件」と呼ばれます。
競売物件は、通常の不動産取引とは異なり、安価で購入できるチャンスがある一方で、独自の手続きや注意点が存在します。
- 通常の市場価格よりも安価で購入できることが多い
- 内覧ができないケースが多い
- 占有者の問題がある場合もある
ここでは、競売の基本的な仕組みから、競売物件の購入の流れや必要な書類について詳しく解説していきます。
競売の基本的な定義と仕組み
競売は、債務者が借金の返済を行わない場合に、裁判所が介入し、その資産を公開の場で入札にかけて売却します。
これにより、債権者は債務の一部または全部を回収することができます。
競売物件の購入者は、入札によって最も高い金額を提示した人が物件を取得する仕組みです。
競売物件の魅力は、市場価格よりも安価に物件を手に入れられる可能性があることです。しかし、事前に内覧できない場合が多く、物件の状態や現状を十分に把握できないというリスクも伴います。
競売物件の購入までの流れ
競売物件の購入の流れは、一般的な不動産取引とは異なり、裁判所を通じた入札方式で行われます。
入札期間内に入札書を提出し、落札後に契約を交わして代金を支払い、所有権が移転するという、一般的な不動産取引よりもシンプルに進行します。
物件の調査
競売に出されている物件の情報を公告や裁判所のサイトで確認し、物件の状態や法的リスクを調べます。
入札の準備
必要な書類(入札書、入札保証金の振込証明書、身分証明書)を準備し、入札に備えます。保証金は物件価格の約20%が目安です。
入札の実施
指定された入札期間中に、裁判所へ入札書を提出します。他の入札者との競争で最も高い金額を入札した人が落札者になります。
残金の支払い
落札後、残りの代金を指定期間内に支払います。この支払いが完了すると、物件の所有権が移転されます。
引き渡しと手続き完了
物件の引き渡しを受け、必要に応じて修繕や立ち退き手続きを行い、物件を利用できる状態にします。
この流れを把握することで、スムーズに競売物件の購入が進められます。
競売物件の入札に必要な書類とは?
競売物件に入札するためには、いくつかの必要書類を揃えて提出する必要があります。
これは、購入希望者が適切な手続きを行い、正当な入札者であることを証明するためです。
主な書類は以下の通りです。
- 入札書:希望する購入価格を記載。
- 入札保証金の振込証明書:物件の評価額の一部を保証金として支払った証明書。
- 身分証明書:個人は運転免許証やパスポート、法人は法人登記簿謄本など。
- その他裁判所が指定する書類:必要な書類は裁判所で確認。
これらを揃えて期日までに裁判所へ提出することで競売物件に入札することができます。
入札後の手続きと注意点
入札後、落札者は以下の手続きを行う必要があります。
- 残金の支払い:指定期間内(通常1〜2か月)に物件代金の残りを支払います。
- 所有権の移転登記:法務局で登記手続きを行い、正式に所有者となります。
- 物件の引き渡し:占有者などがいない場合はすぐに利用が可能です。
これにより、正式に競売物件の所有者として認められます。
ただし購入にあたり、以下の注意点と確認をしっかり行い、リスクを最小限に抑えることが大切です。
- 代金の支払い期限を守る:支払い遅延はリスクが高く、保証金の没収につながることがあります。
- 占有者や物件の状態に注意:引き渡し後もすぐに使用できるとは限らないため、事前にしっかり確認を。
- 修繕費用を想定:物件の状況によっては、修繕やリフォーム費用が必要になることがあります。
競売物件に関するよくある質問
競売物件を購入する際には、多くの疑問や不安があるかもしれません。
以下では、よくある質問に対して詳しくお答えします。
物件購入におけるリスクや手続き、注意点などを理解し、安心して競売物件の購入を進められるようにしましょう。
競売物件を購入する際に注意すべき点として、まずは事前調査の徹底が挙げられます。物件の状態や占有者の有無、修繕の必要性などを事前に把握することが、購入後のリスクを減らすために重要です。また、購入手続きや法律面でのサポートを受けることも推奨されます。
競売物件の主なリスクとしては、内覧ができないため物件の状態が不明であること、不法占拠者がいる可能性があること、リフォームや修繕費が想定以上にかかることなどが挙げられます。これらのリスクを理解し、事前に対策を講じることが重要です。
競売物件の購入には、物件の落札価格に加え、リフォームや修繕費、登記手続き費用、司法書士や弁護士への報酬などがかかる場合があります。購入前にこれらの費用も考慮し、予算を計画的に立てることが必要です。
まとめ
この記事では競売物件がやばいといわれている理由やメリット、そしてリスク回避の方法についてご説明しました。
競売物件がやばいといわれるのは、ハイリスク・ハイリターンだからです。
内覧ができず、資産価値も判別しにくい反面、中には一般的な相場よりも格安で物件が購入できるため、不動産投資でも大きなリターンが期待できます。
リスクは入念な調査で回避できるため、競売物件を選ぶ際は慎重に購入を進めましょう。
専門家の調査や下調べを行い、やばいリスクを回避しましょう。
\最新の競売物件情報をいち早くゲット!/
全国の競売物件を簡単検索&比較!
まずは無料会員登録で、最新の競売物件をいち早くチェックしましょう。